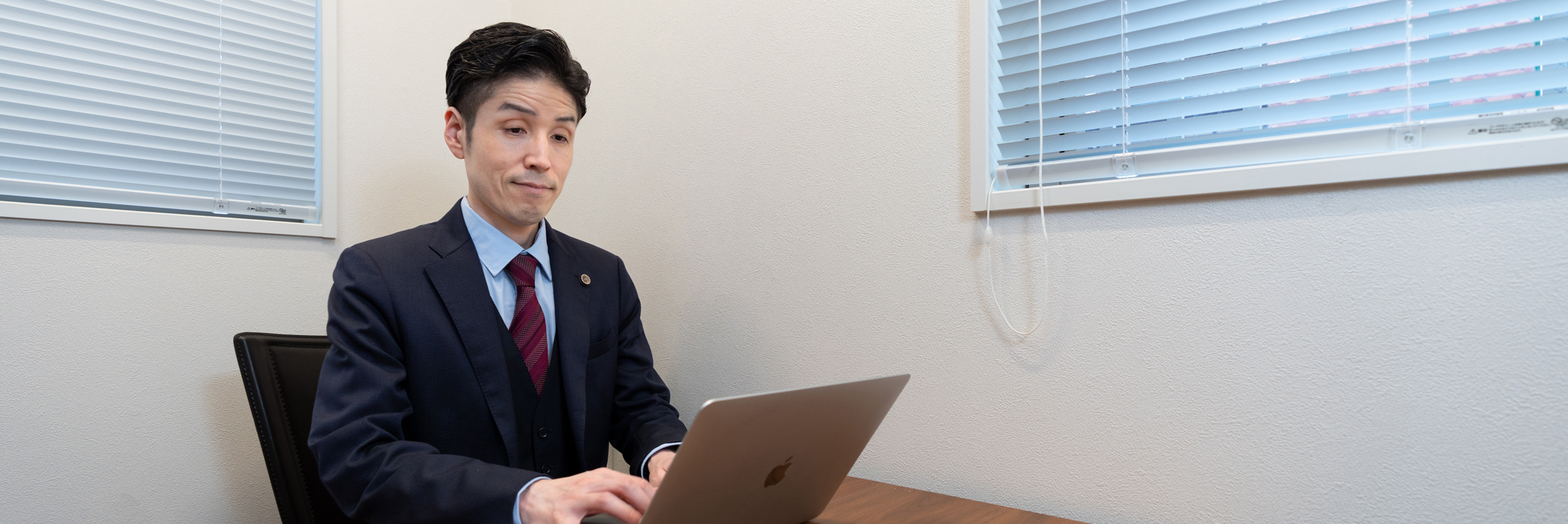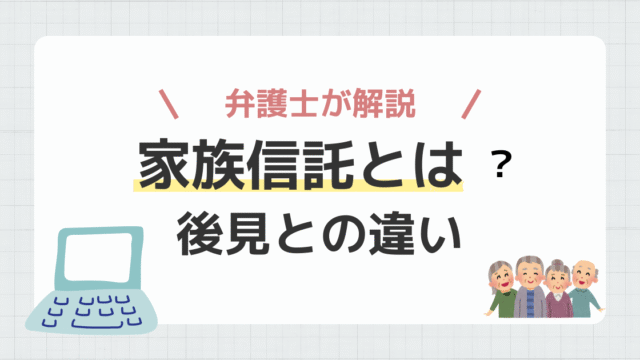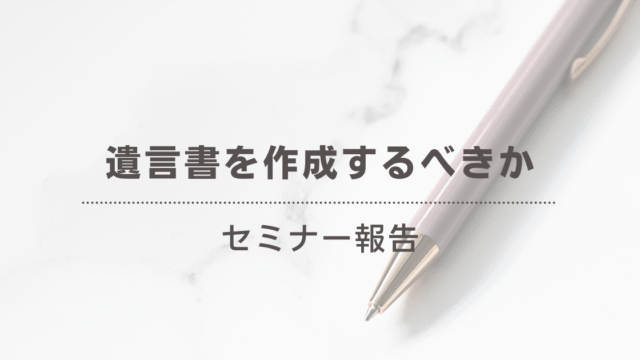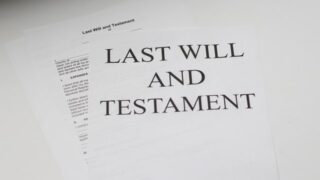離婚後、養育費を支払っている相手方が再婚した場合、養育費の支払義務はどうなるのかという疑問を持った事はありませんか?
この問題について実務経験10年以上有する現役弁護士が解説したいと思います。
相談例
AとBが離婚しました。 Bが子C(3歳)の親権者となり、育てています。
Aは、「BがDと再婚した」ということを偶然知りました。
AがBに対して毎月支払っている養育費はどうなるのでしょうか?
DがCと養子縁組をしていない場合
DはCに対する扶養義務を有していません。
よって、原則として養育費の減額は困難です。
例外
Dが資産家で、B・Cが裕福な暮らしを再婚後にしている、
反面、Aが苦しい生活を続けている
と言うような場合、減額が認められるケースもあります。
Dは配偶者としてBに対する扶助義務を保持しています(民法752条、同760条、なお通説・判例は両者は同じ義務を規定したものであると解釈)。
この扶助義務の履行、つまり、DがBの生活費を負担する行為が「DからBへの所得移転」と解釈され、Bの所得が増変したことにより、あるべき養育費の金額を再検討すべきとなったのでしょう。
【子と養子縁組をしていない権利者の再婚相手の収入の一部を権利者の収入に加算することが認められた事例】
〇再婚相手には子を扶養する義務はないものの、権利者と再婚相手との間には夫婦としての相互扶養義務があり、権利者は子らの母としての扶養義務があることから、少なくとも再婚相手の収入から権利者に対する生活費としての相応の所得移転があるものとみなした事例(大津家審平20・6・10(平20(家)25・平20(家)26))
引用元「個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント 編集/森法律事務所 森公任、森元みのり 新日本法規出版 2020年 7月 277頁」
DとCが養子縁組をしている場合
DのCに対する扶養義務が発生します(民法877条1項、民法818条2項)。
一方、AとCは実の親子でありますので、AはCに対する扶養義務を引き続き有したままです。
この場合、養親Dが実親Aに優先してこの扶養義務を果たすべきとされています。
よって、AはBに対し家庭裁判所において養育費減額の調停を申し立てれば、その減額が認められる可能性が相当程度あります。
Aがそのような調停を申し立てることなく養育費の支払いを任意に止めても、法形式上は従前の養育費請求権がBからAに対して存在したままですので、後から累積分をまとめてBから請求される可能性が高いです。
例外
養子縁組をした再婚相手Dの収入や資力が低く、他方でAには経済的余裕がある
と言う場合は減額が認められない可能性も大いにあります。このあたりはケースバイケースとしか言いようがありません。
参考文献
「相手方の再婚と養育費」についてのより詳しい解説は↓をご参照ください。